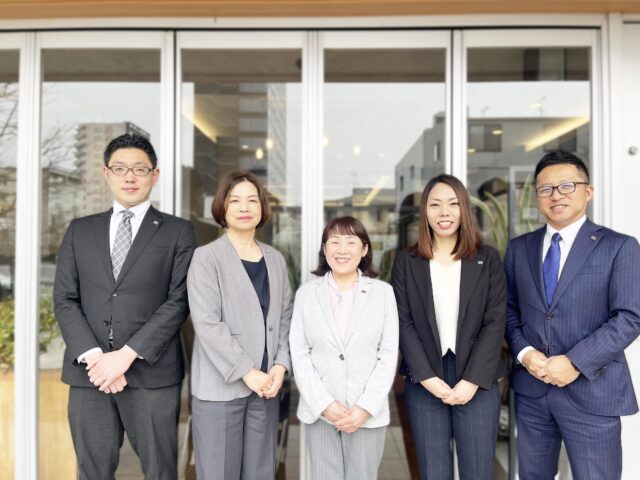【司法書士監修】相続時の不動産売却は?流れや必要書類、注意点を徹底解説
目次
不動産を相続したらどうするべき?
相続で不動産を取得したとき、その活用法には、売る、買う、貸すといった選択肢があります。
今回は「売る=売却」する場合の流れや必要な書類、注意点について、司法書士 渡邉一史さんにお話をお聞きしました。

相続した場合の不動産売却の流れをご紹介
「不動産を相続するとさまざまな手続きが必要になります。
忙しくて手が付けられないこともあるかと思いますが、不動産相続は時間が経つほどに複雑になります。
というのも、新たに相続が発生したり、相続人の気持ちが変わったり、トラブルの原因が発生しがちです。
また、相続で相続税の申告が必要な場合は、相続の発生を知った日の翌日から10カ月以内に相続税を申告して納税まで済まさなければなりません。
いざというときに相続をスムーズにすすめるためにも、不動産売却の流れを知っておきましょう。
①遺言書を確認する
相続のことで多くの方が誤解されていると感じるのは、第一に「法定相続分の権利」を主張されることです。
相続の仕組みとしてまず第一に、遺言書があればその内容に従って相続を進めることになります。
遺言書がなかった場合には、相続人全員で誰が何を相続するのかを話し合います。
相続が発生した時点で、まずは遺言書があるかどうか確認し、亡くなった方がどういう気持ちだったかを確認しましょう
②相続人を確認する
遺産分割協議をする際には、相続人を特定することがとても重要になります。
なぜなら、相続人が漏れていたり、意図的に誰かが外されていたりすると、遺産分割の取り決めの内容が無効になるためです。
亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を取得し、遡って相続人の存在を調べます。
戸籍は分家、離婚や結婚、転籍や養子縁組をした場合に新たに作られ、一生のうちに複数作られます。
亡くなった時点でのご家族が、他にも相続人がいることを知らないことはよくあります。
亡くなって時間が経つと、相続人を確認するのも大変になります。相続が発生した時点で、相続人の確認を進めましょう。
③遺産を分割する
相続人の全員を特定できたら、誰が何を相続するかを話し合う遺産分割協議を行います。
協議書に全員で署名して実印を押し、印鑑証明書をつけます。
相続人の人数が増えるほど遺産分割協議で話をまとめるのが大変です。
相続でもめる最も大きな原因が「遺産分割協議」です。
この場合でも、全員が話し合いますので、法定相続分に拘束されることはありません。
もちろん、法定相続分を目安に分割されても構いません。遺言書があれば話し合いは必要なく、揉めようがありません。
しかし、一般的に遺言書はほとんど用意されていません。
ご自身が相続で揉めた経験のある方は子どもたちに苦労させたくないと準備されます。
遺言書が相続人の幸せにいかに大事であるかがよく分かります。
④不動産の名義変更を行う
数ある手続きの中で、必ず行っていただきたいのが「相続登記」です。
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、これから相続される方(相続人)の名義へと変更することです。
2024年4月から義務化されました。
相続登記の手続きをしないままにして時間がたつと、相続人の気持ちが変わってしまうことがあります。
例えば、相続人のご家族に「お父さんは長男に家を引き継いでもらいたがっていたな」という共通認識があったとします。
お父さまが亡くなった直後はその記憶があり長男が相続することで話がまとまりやすいですが、時間がたって記憶が薄れてくるとご家族の中に「売ってみようか」と気持ちが変化する方がいるかもしれません。
そうなると、話はまとまりません。
名義を変更していない、つまり相続登記をしていない場合、 よくあるリスクとして法定相続分で相続人のうちの一人が他の相続人の同意を得ずに登記をしてしまうケースです。
例えば、相続人が3人、法定相続分が3分の1ずつとします。
遺産分割協議でAさんが相続することになっていたにもかかわらず、Cさんが保存行為として法定相続分の各3分の1の割合で3名の共有名義で登記をし、Cさんの持分3分の1を他人に譲渡する、ということも起こり得ます。
あとで取り返そうと思っても売った相手(第三者)に対抗できません(所有権を主張できない)。
相続登記をしていなかったのが悪い、と言われてしまいます。
昔は共有持ち分だけを買うような人はいませんでしたが、現在はこのような持分だけでも買うという不動産業者が現れています。
Cさんから持分を買い取った後にその持分を買い戻すように言ってくるのです。
昔のようにとりあえず放っておいてもいい、という状況ではなくなっています。
相続登記の手続きは、亡くなった人の出生から死亡までのすべての繋がりが説明できる戸籍謄本、戸籍の附票等の一式、遺産分割協議書、署名押印した相続人の印鑑証明書、相続する人の住民票などが必要です。
法務局に提出し、相続された方の名義に変えます。
⑤不動産会社に査定を依頼し、売却
名義の変更が完了したら、信用できる不動産会社を探して査定を依頼しましょう。
不動産会社の選び方については下記よりご参照ください。
【東広島】不動産売却はどこがいい?売却の動向や相場もご紹介 – 株式会社不動産本舗 (fudosan-honpo.jp)
相続した不動産の名義変更に必要な書類とは
相続には、遺言による相続、遺産分割協議による相続、法定相続分による相続があります。
それぞれのケースで必要な書類が異なります。
こうした書類を個人で準備することもできますが、専門性のある知識に基づいて複雑な手続きを進めていくことになります。
記載に間違いがあると登記ができません。なるべく司法書士や税理士など専門家に代行を依頼されると労力も手間も省けます。
法定相続の場合
法定相続の場合、亡くなった方の出生から死亡までのすべての繋がりが説明できる戸籍謄本一式、そして戸籍の附票が必要です。
戸籍の附票とは、戸籍に付随する本籍地、住所移転の履歴が書いてあるものです。
不動産が昔の住所で登記されていることもあり、同一人物かどうかを確認するために必要です。
相続人の方は、戸籍謄本、印鑑証明書、不動産を相続する方は住所を登録するために住民票が必要です。
不動産に関する固定資産税評価証明書などでお持ちの不動産を確認します。
遺産分割協議による分割の場合
遺産分割協議による場合、前述した法定相続の場合と同じ書類が必要です。
さらに、遺産分割協議書が必要になります。
遺言による分割の場合
遺言により誰がもらうかは指定されているため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本は必要ありません。
遺言の効力が発生したことを証明するために、遺言した方の死亡時の戸籍、戸籍の附票は必要です。
相続する方は、例えば長男が相続されるなら長男を確認できる戸籍謄本、遺言書に記載された住所が変わっている場合は、戸籍の附票、住民票が必要です。
相続した不動産の売却に必要な書類とは
不動産売却をスムーズに進めるために、さまざまな書類が必要になります。
ここでは一般的なものを紹介しますが、そのほかにも必要なものがあります。
必要な書類は不動産会社や司法書士など、不動産売却に詳しい専門家と進められる方がスムーズです。
一戸建ての場合
一戸建ての場合、主に身分証明書、実印、印鑑証明書、登記済権利書または登記識別情報、固定資産税評価証明書が必要です。
相続登記をした後に、住所を変更している場合には、戸籍の附票や住民票が必要になることもあります。
不動産会社や司法書士などに確認しましょう。
※土地を測量されている場合には土地測量図、隣地との境界確定をされている場合には、境界確認書なども引き継ぐ必要があります。
マンションの場合
一戸建ての場合と同様に、主に身分証明書、実印、印鑑証明書、登記済権利書または登記識別情報、固定資産税評価証明書、相続登記をした後に住所を変更している場合には、戸籍の附票や住民票が必要になることもあります。
そしてマンションの管理規約や維持費等の書類も必要です。
土地の場合
土地の場合も、主に身分証明書、実印、印鑑証明書、登記済権利書または登記識別情報、固定資産税評価証明書は必要です。
相続登記をした後に、住所を変更している場合には、戸籍の附票や住民票が必要になることもあります。
※一戸建てと同様、土地を測量されている場合には土地測量図、隣地との境界確定をされている場合には、境界確認書なども引き継ぐ必要があります。
※売却に直接必要な訳でないのですが、共通して注意していただきたい点があります。
亡くなられた人が、不動産を購入あるいは取得した際の売買契約書や建築請負契約書、領収書など取得にかかった費用が分かる書類を保存しておいていただくことです。
自宅を生前に整理する際や相続した際に、もう必要ないだろうと処分されること多々あるようですが、これらの費用が分かる書類があれば、売却した代金から取得に要した費用として差し引くことができる可能性があるので、大切に保管してください。
相続した不動産の売却で注意したいこととは
相続では、相続する方、相続される方、一人一人の思いを丁寧に受け止めながら、必要な手続きをもれなく進めていく必要があります。
相続した不動産の売却で、特に注意したいことを説明します。
共有で登記されている場合、全員の同意が必要である
共有する時点で、売却に関しての気持ちの違いをよく確認していないと後々困ることがあります。
預金が割り切れないことから、相続した不動産の持ち分の金額相当を法定相続分に充てようと、共有で登記されているケースがあります。
例えば、3人で一軒家を相続し、共有で登記。一人は売りたい、一人は売りたくない、もう一人はどっちでもいいと、思いが三者三様の場合、一人でも売りたくない方がいれば売却は実現できません。
共有する全員が「売ってもいい」と同じ意見ならば、ひとまずは共有で登記していても問題ありません。
しかし、人の気持ちは変わるものです。司法書士としては、共有名義は基本的にお勧めしません。
共有で登記せざるをえない場合は、誰と共有するのか、一人一人がどう考えているのかをよく確認して進めてください。
遺言書があれば、一つのゴールに向かって話し合いができます。遺言書がどれだけ大切なのかがよく分かります。
換価分割の場合、遺産分割協議書に目的を明記する
換価分割とは、相続した遺産を売却して金銭に換え、この金銭を相続分に応じて分割する方法です。
換価分割する場合、遺産分割協議書に「下記の不動産については、売却して換価分割を行う」と目的を明記しておきましょう。
その記述がない場合、贈与税や譲渡所得税の問題が発生してしまうことがあります。
例えば、Aさんの名前で登記して売却後にBさんと代金を分けるとしても、税務上はAさん一人が売ったことになります。
代金の一部をもらったBさんに贈与税が課税されますし、AさんはBさんに渡したお金が譲渡所得から引かれません。
こうしたことを避けるために、遺産分割協議書に、例えば「登記名義はAとするが、売却した代金は各相続人に〇%ずつ分配する。それぞれが譲渡所得の申告を行う。」というように可能な限り具体的に書いておきます。売却後にそれぞれが申告する際に便利です。
相続した不動産の売却は3年を目安に行う
相続した不動産を売却した際に利用できる特例がいくつかあります。これらは「3年」をめどに手続きが必要なものがあります。
それらは利用するための条件が細かくありますので、詳しくは税務署にご確認ください。
相続した不動産は節税できる?
これまで、相続で不動産を取得し際の「売却」する場合の流れや必要な書類、注意点について、司法書士 渡部一史さんにお話をお聞きしました。
ここからは、相続した不動産にかかわる税金について不動産本舗から解説いたします。
不動産の売却において、基本的には節税する方法はありません。ただし、次のような特例が用意されています。
取得費加算の特例を活用できる
相続人の負担を減らすために「取得費加算の特例」があります。
相続発生後、3年10カ月以内に相続財産を売却した場合、相続税として支払った金額の一部を負担からはずして、譲渡所得税の節税ができます。
マイホームを売ったときの特例を活用できる
相続し売却した不動産がマイホームの場合(相続人も一緒に住んでいた)、譲渡所得から3,000万円まで控除されます。
空き家を売ったときの特例を活用できる
空き家の放置による周辺の生活環境の悪影響の防止や空き家の有効活用をすすめるため、相続によって取得した古い空き家の売却で、一定の要件のもと居住用財産の3,000万円特別控除が適用される特例があります。
対象となる空き家は昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、売却の際には耐震リフォームするなどして新耐震基準を満たして譲渡する必要があります。
更地で売却する場合にも適用が可能です。
適用期限は平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間で、相続時からその相続の開始があった日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したものに限られます。
家屋や相続人の要件が細かくありますので、詳しくは税務署、税理士にご相談ください。
相続した不動産のご相談は不動産本舗へ
不動産を売却する場合、税法や不動産登記法など、さまざまな知識や経験が必要になります。関係する各種分野の専門家と提携していますので、窓口となって皆さまの不安や疑問におこたえし、ノンストップでスムーズな売却を実現させていただきます。
また、信頼できる専門家を紹介させていただくことも可能です。
被相続人が亡くなって数年たって相続に着手された場合、亡くなった方の意思が影響されず揉めるケースがよくあります。
どのように相続するか、いくら手元に残るのかも大事なことなのですが、故人が一番に望まれていることは、相続された方々がこれからも幸せに過ごされることだと思います。
不動産本舗ではお客様の思いをしっかり受け止め、大切な不動産を活かす方法をご提案させていただきます。
まとめ
相続は、いずれはどうにかしないといけない問題です。
子や孫の代まで問題を引きずってしまうよりも、ご自分の代で解決された方が安心ではないでしょうか。
また、物件は時間がたつほど価値が下がります。
人が住まない家は傷むスピードが早いということは、皆さんもよくご存じだと思います。
相続が始まったら、司法書士や弁護士などの専門家をまじえて、なるべく早めに協議されることをお勧めします。
記事を書いた人
- 東広島市で産まれ、前職から不動産業に携わって約25年、お仕事を通じて地域の皆様に育てていただきました。業者都合の提案ではなく、お客様にとって本当に価値のあることは何かを考え、本物の価値を提供することが、私の使命と感じています。お困り事、お悩み事がございましたら、まずは当社にお気軽にご相談下さい。
新着の記事
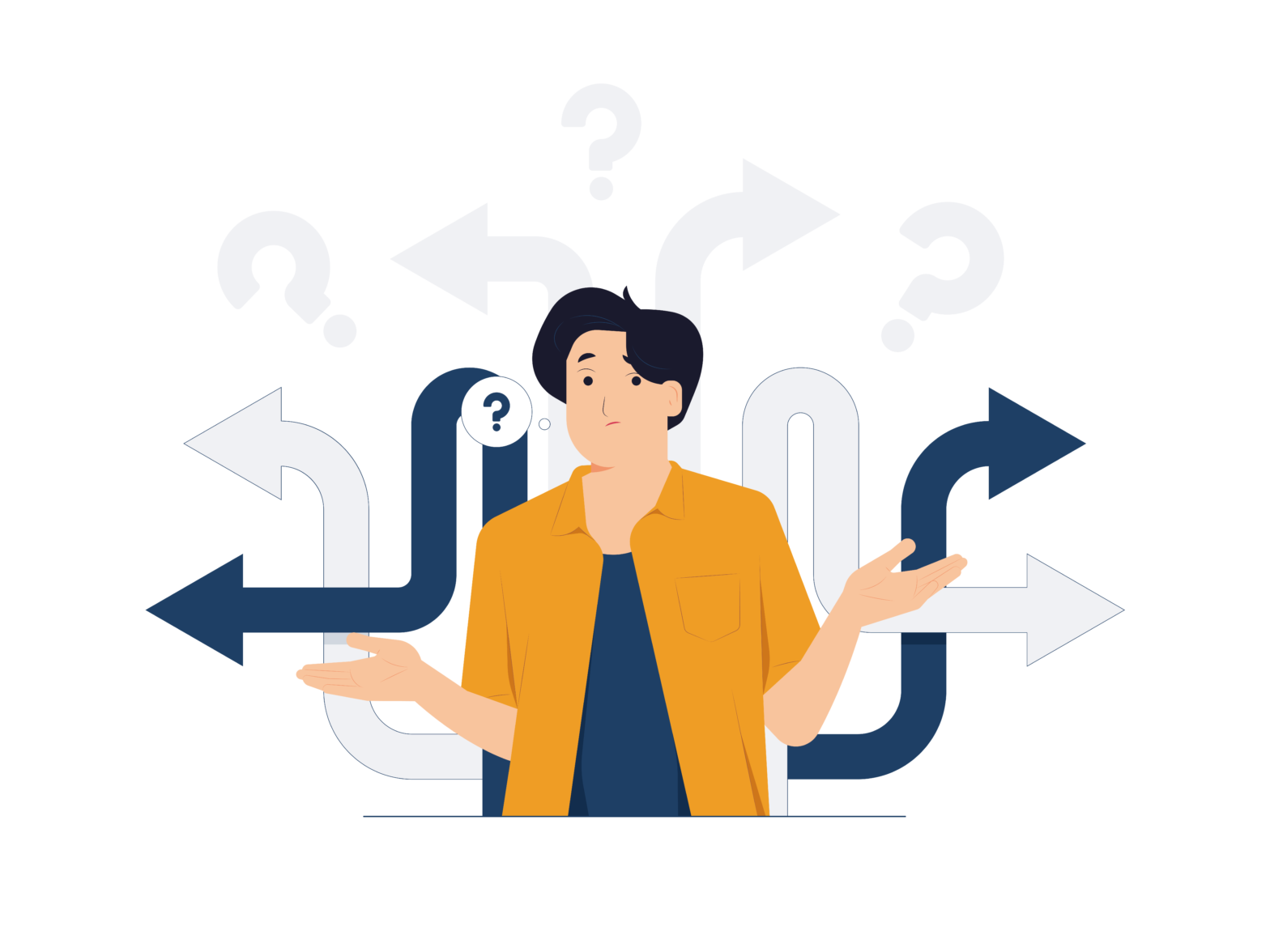 不動産購入2026年1月20日【土地の購入】ベストタイミングはいつ?東広島のケースを詳しく解説
不動産購入2026年1月20日【土地の購入】ベストタイミングはいつ?東広島のケースを詳しく解説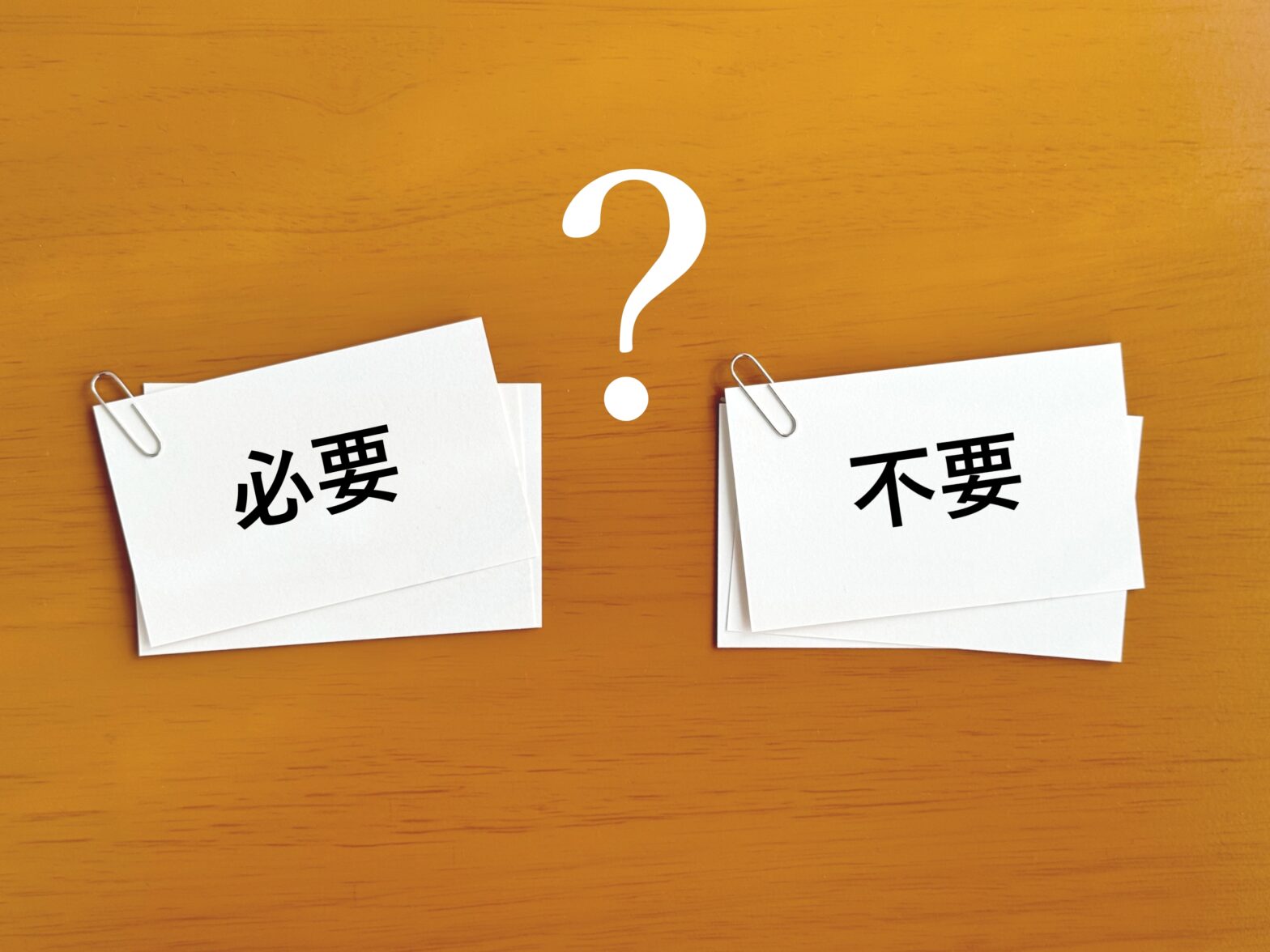 不動産購入2025年12月13日【税理士監修】不動産の購入で確定申告は不要?必要なケース&方法を解説
不動産購入2025年12月13日【税理士監修】不動産の購入で確定申告は不要?必要なケース&方法を解説 不動産購入2025年11月15日【土地の購入】諸費用はいくらかかる?内訳&シミュレーションで誰でもわかるポイントを解説
不動産購入2025年11月15日【土地の購入】諸費用はいくらかかる?内訳&シミュレーションで誰でもわかるポイントを解説 不動産購入2025年10月14日土地の購入の流れとは?東広島ならではの土地事情も詳しくご紹介
不動産購入2025年10月14日土地の購入の流れとは?東広島ならではの土地事情も詳しくご紹介